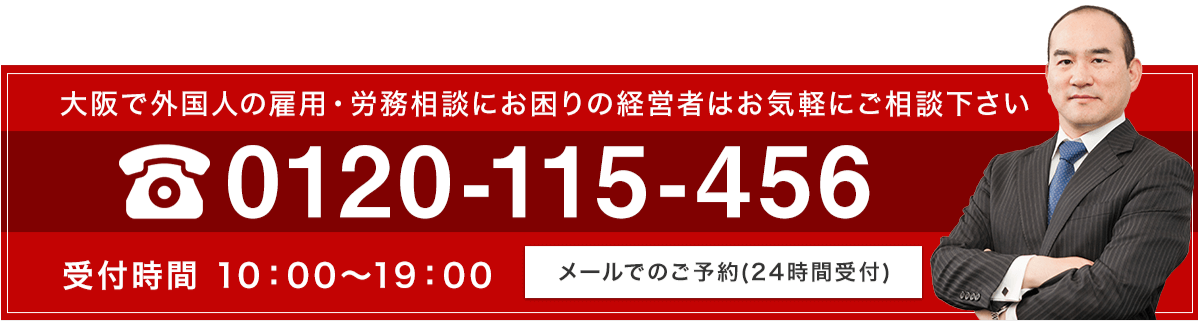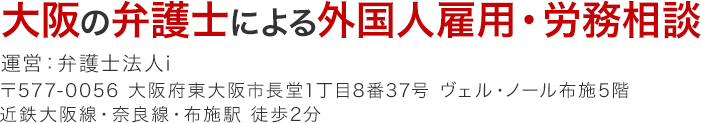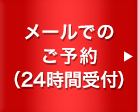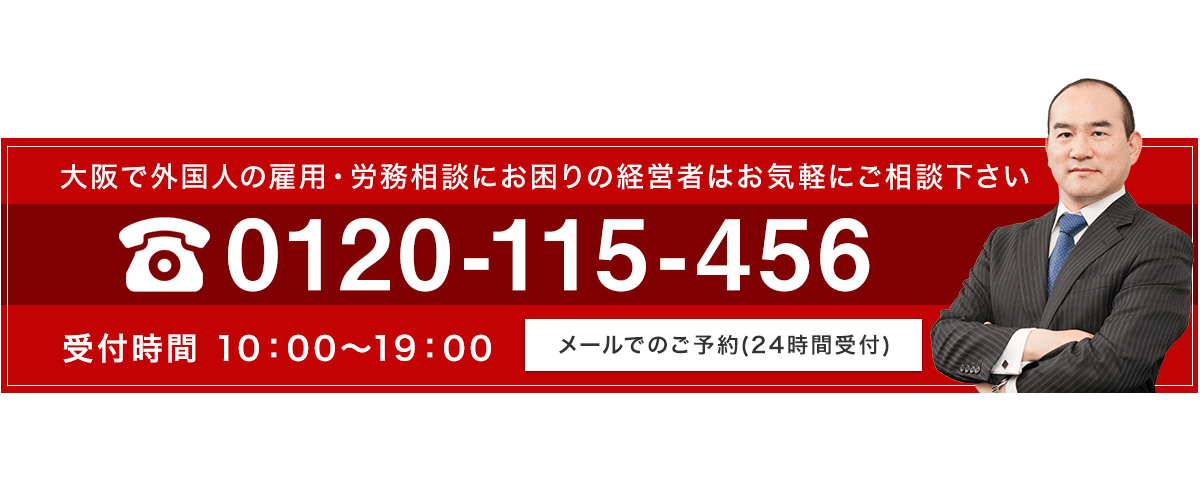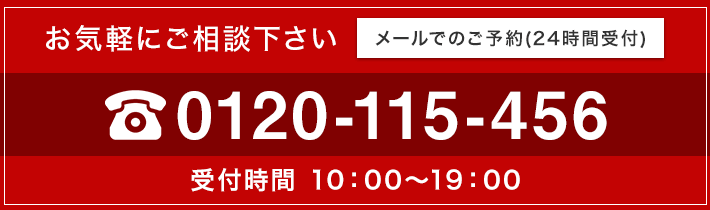【外食業】外国人材雇用のポイントについて解説
特定技能「外食業」
在留資格「特定技能」とは、2019年4月に新設された、人手不足を補うための日本の制度です。「特定技能」を取得した外国人材は、人手不足が深刻化している業界で、規定の期間、日本での就労が認められます。
その特定技能制度の1つが「外食=外食業分野」です。特定技能には1号と2号があり、「外食業」分野は1号のみでしたが、2023年秋に外食業も特定技能2号の対象となりました。
また、特定技能「外食業」は、外食業の範囲内であれば、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)のような業務制限がほとんどありません。日本人を雇用する場合に近しい業務ができ、アルバイト雇用とは違い継続的な育成・スキルの蓄積などを行っていくことができます。
職種
飲食店、持ち帰り 飲食サービス業、配達飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス業を行っている事業所で就労可能です。
例:食堂,レストラン,料理店,喫茶店、ファーストフード店、
テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、
仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、ケータリ ングサービス店,給食事業所(客の求める場所において調理するもの) など
業務内容
1号特定技能外国人が従事する業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)です。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(店舗において 原材料として使用する農林水産物の生産、店舗における調理品等以外の物品の販売等)に 付随的に従事することは差し支えないとされています。
2号特定技能外国人が従事する業務は、外食業全般(飲食物調 理、接客、店舗管理)に加えて、店舗経営の業務についても対象となっています。 なお、例えば、店舗経営・管理業務を主として従事し、接客、飲食物調理 を行うことも可能です。 店舗経営とは、店舗をトータルで管理するために必要な飲食物調理、接客、店舗管理の業務以外のもの(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)です。
なお、特定技能外国人の雇用は直接雇用とし、フルタイム*で業務に従事するものであることが必要です。 (*本制度におけるフルタイムとは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働 時間が30時間以上であることをいう。)
特定技能外食の取得要件
特定技能「外食業」1号の在留資格を取得するには以下のどちらかの要件を満たす必要があります。なお、年齢要件は18歳以上の男女です。
要件1:特定技能試験に合格する
「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格する必要があります。
要件2:技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ移行する
技能実習2号を良好に修了、または技能実習3号の実習計画を満了することで在留資格の変更申請が可能です。
外食業分野への移行対象は「医療・福祉施設給食製造職種」のみが対象となります。
日本語能力試験
日本語能力試験は「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(200点以上)」のどちらかを受験します。どちらを選んでも問題ありません。
日本語の能力試験の認定目安は以下の通りです。
N1:幅広い場面で使われる日本語を理解することができる
N2:日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる
N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
N4:基本的な日本語を理解することができる
N5:基本的な日本語をある程度理解することができる
日本の四年制大学に通う留学生の多くはN2の取得を目指しており、最難関のN1の合格率は国内外合計で30%程度となっています。
技能水準試験の合格
外食業特定技能1号技能測定試験の試験科目は「学科試験」と「実技試験」の2科目70分で行います。
試験の内容は外食業の仕事内容についての技能水準を問うもので、学科試験は外食の業務に必要な日本語能力を、実技試験は正しい行動の選択と作業計画を立てられるかの能力を測ります。
試験は1年通して3回、大まかに3月、8月、11月頃に行われ、事前のマイページの申請が必要となります。日本国内会場と海外の会場で実施されていて、海外はフィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマー、カンボジア、タイ、スリランカで実施されています。
| 学科試験の内容 | ・ 衛生管理:食中毒や冷蔵庫の温度、交差汚染などの衛生管理のほか、HACCPに対応した衛生管理l 飲食物の調理:食材の管理、下処理、各種調理法による基礎知識 ・接客全般の知識:接客サービスのほか、食物アレルギーに対する知識、店舗の管理、顧客へのクレーム対応など |
| 実技試験の内容 | ・判断試験:図やイラストを使った正しい行動かの判断l 計画立案試験:決められた計算式を使った作業の計画 |
試験は「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」の3科目で出題されます。
以下に、特定技能「外食」の試験問題・内容例をご紹介します。
- 衛生管理編
1:基本的な衛生管理の知識
・食中毒に関する基礎知識
・食中毒予防3原則
・食中毒をひきおこす代表的な細菌やウイルス
2:一般的衛生管理の知識
・原材料の受け入れの確認
・冷蔵、冷凍庫の温度管理
・交差汚染、二次汚染の防止
・調理器具などの洗浄、消毒、殺菌
・トイレの洗浄、消毒
・従業員の健康管理、衛生的な作業着の着用など
・衛生的な手洗いの実施
・清掃管理(調理場)及び廃棄物処理について
3:HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の知識(重要管理のポイント)
・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは
・重要管理のポイントについて
・グループ1:「加熱しないもの」の管理方法について
・グループ2:「加熱するもの」の管理方法について
・グループ3:「加熱と冷却をくりかえすもの」の管理方法について
・その他の重要な管理ポイントについて
・衛生管理の記録について
- 飲食物調理編
1:食材(原材料)に関する知識
・肉類について
・魚介類について
・野菜・果実類について
2:下処理に関する知識
・下処理の目的
・野菜の下処理について
・魚介類の下処理について
3:各調理法に関する知識
・加熱調理
・非加熱調理
4:調理機器・調理器具・備品などに関する知識
・調理機器について
・調理器具・備品などについて
・計測機器類について
5:労働安全衛生に関する知識
・調理場における労働安全衛生
・調理機器、調理器具・備品の取り扱いについて
・その他器具・備品の取り扱いについて
・火災防止対応
- 接客全般編
1:接客に関する知識
(1) 接客サービスについて
(2) 接客における基本動作
(3) 食事のマナーについて
(4) 配慮が必要なお客様への対応
(5) 適切な配膳(サービング)について
(6) 接客基本用語とその使い方
2:食に関する知識
(1) 食物アレルギーについて
(2) お酒の取り扱いについて
(3) 栄養について
(4) 味覚について
(5) 食の多様化について
3:店舗管理に関する知識
(1) 営業準備、閉店作業
(2) 清掃作業(調理場以外)
(3) 現金とキャッシュレス決済の知識
4:クレーム対応に関する知識
(1) お客様からのクレームに対する対応
(2) 異物混入発生時の対応
5:緊急時の対応に関する知識
(1) 体調不良者が発生した場合の対応
(2) 災害が発生した場合の対応
これら①~③の3つの科目から試験問題は出題されます。ちなみに、国外で試験を受けるには「フィリピン」「カンボジア」「ミャンマー」などで受けることができます。
試験のタイプ
特定技能「外食」の試験は3つにタイプが分かれます。
それぞれのタイプでは、配点が異なることもあり、自分で好きなタイプを選んで受けることも可能です。
Aタイプ :一番標準的な配点です。
Bタイプ :飲食物調理の配点が高く、その代わりに接客全般の配点が低いです。
Cタイプ:接客全般の配点が高く、その代わりに飲食物調理の配点が低いです。
学科試験は、CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)が用いられ、ペーパーテストで合格基準点を目指します。
試験では筆記試験の他に、実技試験があります。
実技試験では、図やイラストを用いて正しい行動ができるかの「判断試験」と決まった計算式を使って作業の計画を立てることができるかの「計画立案試験」が実施されます。
合格基準点は、学科試験と実技試験で合計得点の65%以上です。
ただし、実施方法によっては合格基準の調整が行われることがありますので、あくまで目安となる基準点です。どのタイプでも衛生管理だけは、同等のレベルが要求されますので、試験を受ける際には必ず出題される衛生管理を重点的に勉強するのをおすすめします。
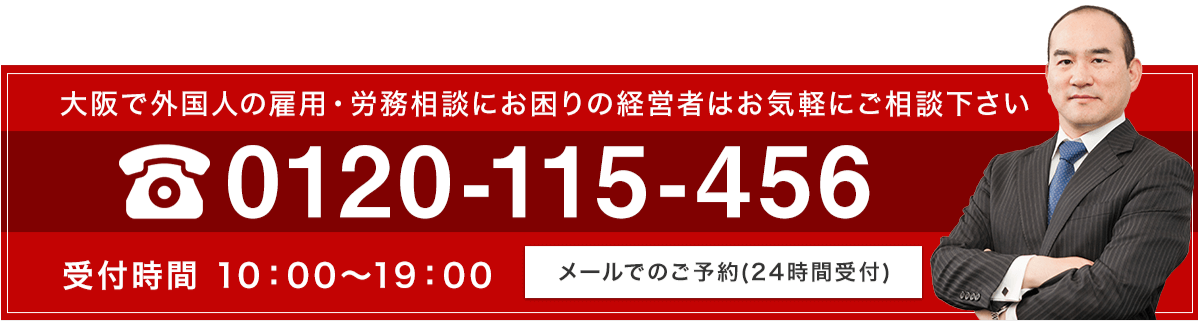
特定技能2号の解禁と要件
2023年に特定技能2号の分野がそれまでの2分野から11分野へと広がり、外食業も特定技能2号の対象分野となりました。
特定技能2号は、特定の産業分野において習熟した技能を持つ外国人が取得できる在留資格ですが、その分、要件も1号より難しくなっています。特定技能2号は家族の帯同が可能で、在留期限の更新回数に上限がないので、長期的な就労が可能です。また、在留期限を更新し続けることにより、永住権を取得できる可能性もあります。
このようなメリットから、特定技能2号の取得を望む外国人材が増えています。特に外食業では、店舗運営やマネジメント業務を担う人材としての活躍も期待され、企業にとっても長期的な戦力としての採用が可能になるのが大きな魅力です。
ただし、外食業で特定技能2号の在留資格を申請するためには、2種類の試験の合格と、規定の実務経験がなければいけません。
<必要な試験と実務経験>
「外食業特定技能2号技能測定試験」への合格
「日本語能力試験(JLPT)」N3以上への合格
指導・管理などの2年間の実務経験
それぞれの要件を順に詳しく見ていきます。
【外食業特定技能2号技能測定試験】
外食業における特定技能2号の技能試験で、「一般社団法人外国人食品産業技能評価試験(OTAFF)」が主催している試験です。
<試験の概要>
日本における外食分野における知識や技能を試す試験
・接客全般
・飲食物調理
・衛生管理
・店舗運営に関する知識 など
現状では、特定技能外国人が個人で受験申請をすることはできません。特定技能外国人を雇用している企業が申し込みます。申し込みのためには、企業登録申請締め切り日までにマイページ登録が必要です。本登録として企業の詳細情報を登録しなければいけないので、スケジュールに余裕をもって行う必要があります。
合格基準:満点(250点)の65%以上
「一般社団法人日本フードサービス協会」のサイトから、学習テキストを取得することができます。
▶ 外食業技能測定試験学習用テキスト|一般社団法人日本フードサービス協会
https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/
<受験資格>
次のア~エの全てを満たす人です。
ア. 試験の日に在留資格を有する人
イ. 試験日の時点で満17歳以上である
ウ. パスポートの所持
エ. 試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイトや特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、サブリーダーや副店長など店舗管理を補助する実務経験(指導実務経験)を2年以上有する、または試験の前日までに指導実務経験を2年以上有することが見込まれること
※「エ」は先述した実務経験を指す
<テスト方式>
試験は学科試験と実技試験の2科目で、試験時間は70分、言語は日本語で出題されます。なお、漢字にルビはついていません。ペーパーテストでマークシート形式です。
<試験科目>
試験は、学科試験と実技試験で行われます。出題範囲は以下の通りです。
学科試験の出題範囲:衛生管理、飲食物調理、接客全般及び店舗運営に係る知識を測定。
| 項目 | 主な内容 | 問題数 | 配点 |
| 衛生管理 | ・一般衛星に関する知識 ・HACCPに関する知識 ・食中毒に関する知識 ・食品衛生法に関する知識 | 10問 | 満点:40点 |
| 飲食物調理 | ・調理に関する知識 ・食材に関する知識 ・調理機器に関する知識 ・食品の流通に関する知識 | 5問 | 満点:10点 |
| 接客全般 | ・接客サービスに関する知識 ・食の多様化に関する知識 ・クレーム対応に関する知識 ・公衆衛生に関する知識 | 10問 | 満点:30点 |
| 店舗運営 | ・計数管理に関する知識 ・雇用管理に関する知識 ・届出関係に関する知識 | 10問 | 満点:40点 |
| 合計 | 合計35問 | 合計120点 | |
実技試験の出題範囲:業務上必要となる技能水準を測定。
| 項目 | 主な内容 | 問題数 | 配点 | ||
| 判断試験 | 計画立案 | 合計 | |||
| 衛生管理 | 学科試験と同じ | 3問 | 2問 | 5問 | 満点:40点 |
| 飲食物調理 | 3問 | 2問 | 5問 | 満点:20点 | |
| 接客全般 | 3問 | 2問 | 5問 | 満点:30点 | |
| 店舗運営 | 3問 | 2問 | 5問 | 満点:40点 | |
| 合計 | 計12問 | 計8問 | 計20問 | 合計130点 | |
<試験の実施状況>
現状では国内でのみ実施されています。特定技能1号のように国外での試験はありません。年に3回程度実施されています。各回のくわしい試験日程は、決まり次第「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)」のサイトで確認できます。
▶ 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
<合格率>
受験者の合格率は平均で40%を超えています。外食業分野は他の分野に比べて受験者数が多く、合格率も高い傾向にあります。
試験サンプルは公開されていませんが、学習用のテキストを見ると、指導・監督、管理する立場などの知識が必要であるということがわかります。特定技能2号の外国人には店長補佐のような業務に就くことが求められるため、試験ではその適性が測られます。
▶ 特定技能2号試験学習用テキスト|一般社団法人日本フードサービス協会
https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/
【日本語能力試験(JLPT)のN3以上】
在留資格の申請前までに合格していなければなりません。特定技能2号の取得要件として、他の多くの分野では日本語能力試験への合格は含まれていないため、これは外食業の特徴といえます。
N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できることが必要」というレベルの日本語力だとされています。
なお、特定技能1号の申請に必要な日本語試験はJFT-basicも対象でしたが、2号からはJLPTに限定されますので、注意が必要です。
【必要な実務経験】
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を受けた飲食店での2年間の実務経験が必要です。
この実務経験では、複数のアルバイトや特定技能外国人の指導・監督をしながら接客業務を行いつつ、副店長やサブマネージャーとして店舗管理の補助を担当した経験が求められます。つまり、単に店舗で勤務するだけではなく、管理業務に携わった経験も求められます。その経験の証明として、副店長やサブマネージャーの肩書きを付与した辞令書や職務命令書、シフト表の提出が必要です。
注意点は、技能実習や家族滞在、留学の在留資格の期間中の業務経験はこの要件に該当しないという点です。また、外国人の母国での経験も含まれません。
<経過措置について>
外食業では、2023年6月10日に外食業が特定技能2号の対象分野となったことを受けて、実務経験について経過措置があります。
2023年6月10日時点で特定技能1号としての在留期間上限の日が「2年6カ月未満」だった場合、そこから6カ月を減じた分だけ管理・指導等の実務経験があれば、実務経験を満たしたことになります。つまり、経過措置の対象である場合、2年に満たなくても実務経験の必要条件を満たしていることにできる可能性があります。
【必要な申請書類】
特定技能2号「外食業」の申請にあたり、全分野に共通の書類とは別に必要な書類は
下のとおりです。
・外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
・日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
・保健所長の営業許可証または届出書の写し
・外食業分野での特定技能外国人の受入れに関する誓約書
・協議会の構成員であることの証明書
・指導等実務経験証明書等(外食業)
これらの書類を揃えて申請することで、特定技能2号「外食業」の在留資格を取得できます。
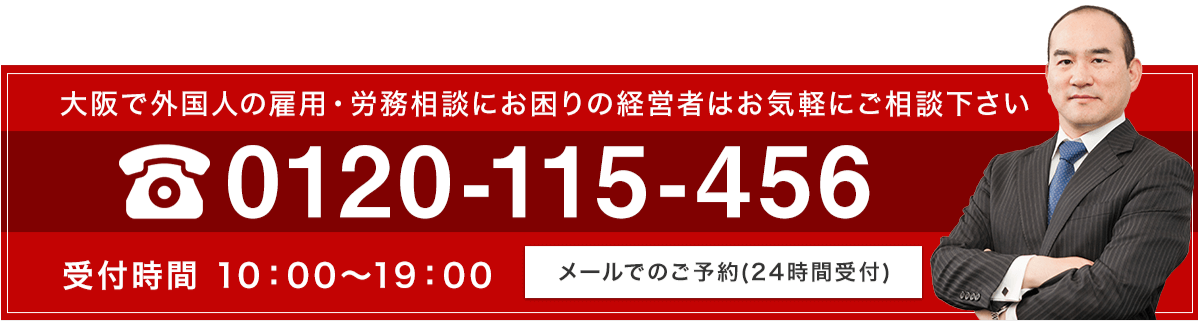
特定技能2号の取得手順
特定技能2号の取得手順は以下の①~④の流れが基本です。
1.特定技能1号外国人にサブリーダーや副店長などの役割を任せ、複数のアルバイトや特定技能外国人の指導・監督や店舗管理の補助を原則2年間経験させる
2.JLPTのN3以上を受験、合格する
※JLPTが外食業特定技能2号技能測定試験の受験後という場合もあります。
3.1. の実務経験2年を満たしたタイミングで、外食業特定技能2号技能測定試験を受験、合格する(この際に①の経験・肩書を証明するものが必要)
4.在留資格変更許可申請書などの2号の申請に必要な各種書類を用意し、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)に提出する
受け入れ企業(特定技能所属機関)の注意点
特定技能「外食」の制度を活用し、外国人人材の受け入れ先となる企業は、一定の条件を達成する必要があります。
・食品産業特定技能協議会の加入
・接待飲食の営業はさせない
・外国人の賃金は日本人と同等
協議会への加入をすること
条件の1つに「食品産業特定技能協議会の加入」があります。協議会は農林水産省が運営しており、構成員にならなければ外国人の雇用はできません。
食品産業特定技能協議会は、外国人の受け入れ状況を把握するのみならず、不正行為の防止などにも役立っています。外国人を雇用する際は、必ず協議会の構成員になる必要がありますので注意が必要です。ちなみに、加入の期限は外国人を受け入れてから4か月までとなっています。
なお、2024年6月15日以降は、受け入れから4か月以内ではなく、事前申請に変更されていますので注意が必要です。
【加入のタイミング】
1. 令和6年6月14日より前に、出入国在留管理庁へ特定技能に関する在留諸申請が完了している場合;
従来通り、初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に、協議会に加入が必要
2. 初めて特定技能外国人を受入れ予定で、これから出入国在留管理庁へ手続きを行う計画がある場合:
出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、協議会に加入が必要
※2人目以降の受入れの際に、改めて加入申請は不要
※協議会加入審査には1~2カ月を要するので、計画的に申請をする必要がある
※詳しくは農林水産省が発表している「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」を参照。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html
※出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会について」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/kyougikai-21.pdf
接待飲食はさせないこと(※法改正により緩和あり)
接待飲食等営業で就労するのは禁止行為にあたります。これは風俗営業法の規定に基づくもので、キャバレーなどの接待に低賃金で外国人を雇うことを防ぐためです。
法律上ではキャバレーやクラブなどの接待飲食等営業では外国人を雇わないことが明文化されています。フィリピンパブなどは本来違法行為にあたり、度々警察による摘発が行われています。接待飲食等営業では、外国人の業務の役割が接待に当たらなくてもそこで働くこと自体が禁止となっています。
「接待」の禁止
上記以外の通常の外食産業であっても、接待は禁止されています。具体的には、歓楽的雰囲気でお客をもてなす行為自体が禁止となります。例えば、カフェや喫茶店でもバーがある場合、お客のグラスにお酒を注いであげるなどの行為も接待行為とされて禁止なので注意が必要です。
賃金要件を日本人と同等にすること
外国人材だからという理由で賃金を下げることはできません。外国人材の賃金は日本人スタッフと同等以上である必要があります。
企業内で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に不合理な待遇差が生まれることを避けるため施行された「同一労働同一賃金制度」は、外国人にも適用されます。外国人材に対する差別が起こらないように注意する必要があります。
外食分野における特定技能採用の流れ
ここでは、「海外にいる外国人を日本に呼び寄せて特定技能1号外国人として雇用する場合」における流れを説明します。外国人本人はあらかじめ試験に合格しておく必要があります。
- 「特定技能雇用契約」を締結する
受入れ希望企業はオンラインなどで面接などを行い、採用する外国人を決め、「特定技能雇用契約」を結びます。
- 「1号特定技能外国人支援計画」を作成する
企業は、特定技能1号の外国人を雇用する場合、雇用する外国人がスムーズに業務に従事し、問題なく日常生活を送れるように支援を行うことが制度上で義務付けられています。
「1号特定技能外国人支援計画」は、企業が外国人に対して実施するサポートを計画したものです。
作成した支援計画書は外国人本人に写しを交付し「十分に理解した」という署名をもらいます。そのため、内容は外国人本人が理解できる言語で説明する必要があります。
- 事前ガイダンスを実施する
企業が外国人に対してテレビ電話などにより事前ガイダンスを実施し、健康診断を受けさせます。これは特定技能外国人支援計画に含まれている支援の一つです。
- 在留資格を申請する
企業が在留資格認定証明書交付申請書を提出し、特定技能「外食業」を申請します。提出先は、申請代理人となっている職員の勤務地を管轄する出入国在留管理庁となります。
この際、健康診断の診断書も必要です。
- 「在留資格認定証明書」を外国人に郵送する
審査が通ると、「在留資格認定証明書」が交付されます。交付されたら海外にいる外国人本人に郵送します。電子メールで交付された場合は外国人にメールを転送します。
- 外国人が現地で査証(ビザ)を申請する
外国人が「在留資格認定証明書」を現地の日本大使館などに提出し、「査証(ビザ)」を申請し、受け取ります。
- 外国人が来日し、就労スタート
外国人が査証と在留資格認定証明書を持って来日し、就労するという流れになります。在留資格認定証明書の有効期限は、発行から3か月以内です。
ここまでの流れの中で、事前ガイダンスなど、特定技能外国人支援業務は、登録支援機関へ委託することも可能です。
※技能測定試験合格者以外も選考対象にして求人募集を行う
特定技能「外食」の試験開催日数は年に数回しかないため、試験合格者のみに絞って求人を出すと応募者が少ない可能性があります。
技能測定試験合格者以外も選考対象にして求人募集を行うと、より多くの外国人材に出会うことができ、雇用に繋がります。
その一つの方法として、「技能測定試験の合格を条件として雇用する」と求人票に記載することで、これから試験を受ける外国人も含め、採用の候補者に加えることができます。
※技能測定試験の代理登録を行う
特定技能試験の合格を前提にして内定している、もしくは特定技能への在留資格変更を前提にして雇用予定の外国人の場合、企業から特定技能試験に代理登録が可能です。
無抽選で受験の席を確実に確保するために行われますが、申し込み多数の場合は抽選が実施されます。
試験のスケジュールは、都道府県によって異なるため、OTAFF一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のホームページを確認してください。フィリピン、インドネシア、ネパールをはじめ、海外会場でも受験できます。
外国人材の活用は是非ご相談ください