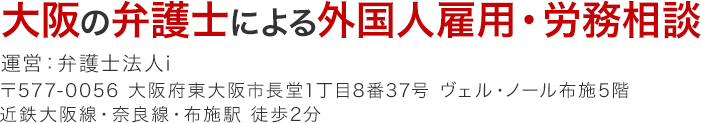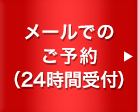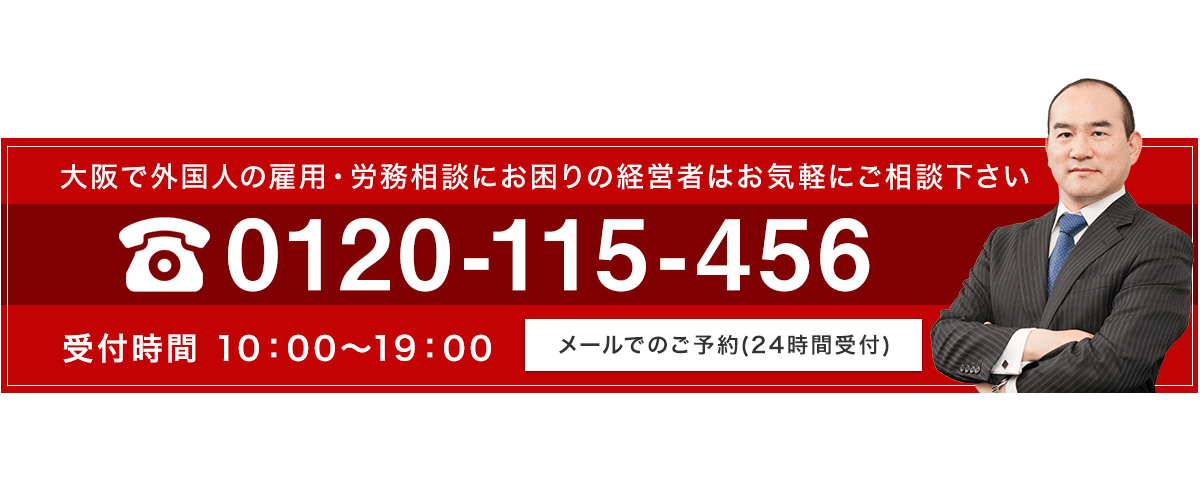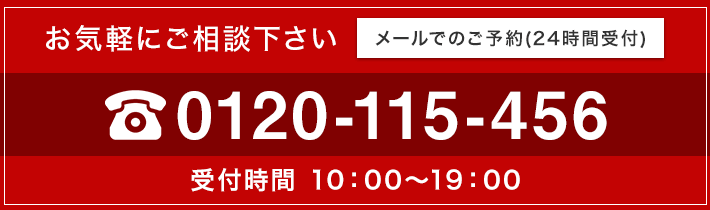技能実習生の雇用・検討されている企業様へ
技能実習制度とは
ここでは、技能実習制度の制度背景、対象となる職種、在留期間、「育成就労制度」への移行について解説します。
①制度背景
技能実習制度は、日本の技術や知識を開発途上国の人材に伝えることを目的とした制度で、1993年に創設されました。技能実習生は、工業、農業、漁業などの分野で技能を習得し、母国に帰国後、その技術を活かして経済発展に貢献することが期待されています。
技能実習制度は「労働力の確保」を目的とした制度ではなく、あくまで国際協力の一環として設計されています。そのため、企業が技能実習生を受け入れる際には、技能移転の意義を理解し、適正な雇用環境を整備することが求められます。
②対象となる職種
技能実習の対象となる職種は、建設業、食品製造業、機械・金属加工、農業、介護など、多岐にわたります。
特に近年、介護や宿泊業といった分野での受け入れが増加しており、人手不足を補う手段としての活用が進んでいます。ただし、各職種には技能実習の要件が定められているため、企業は事前に確認することが必要です。
③在留期間
技能実習生の在留期間は最大5年間で、習得する技能レベルに応じて技能実習1号・2号・3号に区分されます。
・技能実習1号(1年目):基礎技能を習得する期間
・技能実習2号(2〜3年目):習得した技能をより深める期間
・技能実習3号(4〜5年目):優良な受け入れ機関のみが受け入れ可能
技能実習生が長期間日本で働くには、所定の試験に合格し、適切な評価を受ける必要があります。
④「育成就労制度」への移行について
政府は技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を創設することを決定しました。2024年6月の改正出入国管理法の成立により、技能実習制度は廃止され、2026年〜2027年を目処に育成就労制度へ移行する予定です。
この新制度は、技能移転の目的を維持しつつ、外国人労働者の人材確保にも対応する仕組みです。従来の技能実習制度では、在留資格を段階的に更新する必要がありましたが、育成就労制度では一貫して3年間の在留資格が付与され、その後は特定技能1号への移行が可能となります。
また、企業単独型技能実習は「単独型育成就労」として存続し、海外事業所の職員を日本に招聘する形態も引き続き認められます。
大きな変更点の一つが転籍(受け入れ先の変更)の柔軟化です。現行制度では「やむを得ない事情」がある場合に限られていましたが、新制度では「本人の希望」による転籍も一定の条件のもとで認められる見込みです。また、転籍時には転籍先の企業が前職の企業へ補償を行う制度も検討されています。
移行スケジュールとしては、2024年6月に法律が成立し、施行は2027年を予定しています。これに伴い、受け入れ企業は新制度への適応準備が求められるため、早めの対応が必要です。
技能実習生受け入れ企業の要件
技能実習生を受け入れる企業は、以下の要件を満たす必要があります。
①技能実習責任者・生活指導員の配置
技能実習生を適正に受け入れるため、企業は以下の役職を設置する必要があります。
・技能実習責任者:技能実習全般の管理を行う
・生活指導員:技能実習生の生活面をサポートする
・技能実習指導員:業務上の技能指導を担当する
これらの責任者を配置し、実習生が安心して働ける環境を整えることが求められます。
②雇用条件・社会保険や労働保険への加入
技能実習生は、労働基準法や最低賃金法の適用対象となります。そのため、企業は以下の要件を満たす必要があります。
・適正な労働条件の確保(最低賃金以上の給与支払い、時間外労働の管理)
・社会保険・労働保険への加入(健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険)
技能実習生に対する不適切な労働環境が問題視されるケースも多いため、労働基準法を遵守し、適正な管理を行うことが重要です。
③生活支援体制の整備
技能実習生が日本で安心して生活できるよう、企業は以下の支援を提供することが求められます。
・生活に関する日本語指導
・住居の確保(寮の提供、契約サポート)
・医療機関の案内・対応支援
・生活ルールや文化の理解を促すサポート
特に日本語の習得が不十分な技能実習生に対しては、業務指示の伝達がスムーズに行えるよう工夫が必要です。
④実習計画の策定
企業は、技能実習計画を策定し、外国人技能実習機構(OTIT)の認定を受ける必要があります。この計画には、以下の内容を含める必要があります。
・実習の目的
・具体的な業務内容
・技能習得の段階的な目標
・労働条件・勤務時間
実習計画が適切でない場合、認定が下りず、受け入れができなくなるため、慎重に作成する必要があります。
技能実習生受け入れの流れ
技能実習生の受け入れには、「企業単独型」と「団体監理型」の2つの方式があります。
①企業単独型
企業が海外の支店や取引先から直接技能実習生を受け入れる方式です。監理団体を介さないため、企業が技能実習計画の策定、在留資格の申請、入国後のサポートをすべて行う必要があります。
②団体監理型
監理団体を通じて技能実習生を受け入れる方式です。ほとんどの企業はこの方式を採用しています。監理団体が、人材募集、面接、技能実習計画の策定、在留資格の申請、入国後の講習などをサポートするため、企業の負担が軽減されます。
技能実習生受け入れにおけるよくあるトラブル
技能実習生の受け入れには多くのメリットがある一方で、適切な準備や管理が不足すると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
①採用から配属までの期間が長い
【トラブルの原因】
技能実習生の受け入れには通常6から7か月の準備期間が必要です。技能実習計画の認定申請や在留資格の取得、入国後の講習などの手続きが多いため、採用を決めたからといってすぐに人材を確保できるわけではありません。
【解決策】
企業は、受け入れの計画を早めに立て、監理団体と密に連携することが重要です。必要な手続きを理解し、事前準備を進めることで、適切なタイミングで実習生を配属できるようになります。また、人手不足を補うために技能実習生を採用する場合は、余裕を持った採用計画を立てることが求められます。
②技能や日本語能力の不足
【トラブルの原因】
実習生の多くは、来日当初、日本語での意思疎通が十分にできない場合があります。また、業務の経験がほとんどない状態で配属されるため、期待したスキルレベルに達していないこともあります。
【解決策】
事前に日本語能力試験(JLPT N4以上)を採用条件にすることで、一定の日本語力を確保できます。また、受け入れ後も日本語研修を実施し、業務に必要な用語や指示の理解をサポートすることが重要です。さらに、実習生が業務をスムーズに習得できるよう、教育体制を整え、指導担当者を配置することも効果的です。
③労働環境に起因するトラブル
【トラブルの原因】
実習生の労働環境が適切でない場合、トラブルが発生しやすくなります。例えば、賃金未払いや長時間労働、ハラスメント、住環境の不備などが原因で不満を抱えることがあります。こうした問題は、労働基準法や技能実習法に違反する可能性もあるため、注意が必要です。
【解決策】
企業は、労働基準法や最低賃金法を遵守し、適切な労働条件を整備することが重要です。賃金の支払いは、給与明細をわかりやすく作成し、実習生にも十分に説明することで誤解を防げます。また、勤務時間や休憩時間を明確にし、過重労働を避けるよう管理することが必要です。さらに、実習生が快適に生活できる住環境を提供し、困ったことがあれば相談できる体制を整えることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
当事務所のサポート
当事務所では、外国人雇用企業様向けに、以下のようなサービスをご提供しております。
外国人採用支援
貴社で就労をさせたい業務内容をヒアリングしたうえで最適な採用方法をご提案いたします。採用に向けた母集団形成(候補者の確保)も、現地送出機関等と連携をしてサポートが可能ですので、外国人雇用に向けて一貫した支援を行います。
外国人労務顧問
適法な外国人雇用を維持するため、外国人労務に特化した顧問契約を実施しております。顧問契約を通じていつでもお気軽にご相談いただけることで、適法な状態で外国人材の活用を実現できます。
不法就労助長・法令違反対応
外国人雇用においては、「不法就労助長罪」や「資格外活動幇助罪」など様々な法令違反のリスクがあります。「うちは大丈夫」と思っている場合も、しっかりと専門家へのチェックを依頼することをおススメしています。現在の雇用状況に関するリスクチェックのみも対応可能ですので、まずは外国人雇用状況の現状をお聞かせください。